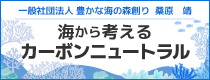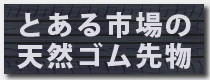連載「つたえること・つたわるもの」(56)
おせち料理は〈神人共食〉、お年玉の由来は〈年魂〉。
連載 2019-01-08
出版ジャーナリスト 原山建郎
正月4日のテレビ放送を見ていたら、昨年11月29日にユネスコ無形文化遺産に登録された「ナマハゲ」(秋田県男鹿市双六地区)をとりあげていた。恐ろしい真っ赤な面をつけ、木製の出刃包丁を持ち、各家々を訪れては「泣く子はいねがー」と叫ぶ、冬の風物詩としてよく知られる、あのナマハゲだが、これまで、衣装の蓑笠や藁靴から落ちる藁屑で家の中が汚れる、酒や食べ物の接待が面倒だなどの理由で、半数以上の家々でナマハゲの来訪が拒否されていたそうだ。また、たとえば双六地区の人口(110人)の約半数が65歳以上と急速に高齢化が進み、若いナマハゲのなり手がいないという悩みもあったそうだ。
ところが、昨秋、ユネスコ無形文化遺産に登録されたというニュースが流れた今年の正月は、ナマハゲの来訪を歓迎する家の数が急増したそうだ。外国からもたくさん観光客がやってきて、なかには「なまはげ体験ツアー」に参加し、にわかナマハゲに扮する外国人も出るほどのフィーバーぶりだったという。
このほか、「ナマハゲ」とともにユネスコ無形文化遺産に一括して登録された8県10行事、「甑島(こしきじま)のトシドン」(鹿児島県)、「吉浜(よしはま)のスネカ」(岩手県)、「薩摩硫黄島のメンドン」(鹿児島県)、「米川(よねかわ)の水かぶり」(宮城県)「遊佐(ゆざ)の小正月行事」(山形県)「能登のアマメハギ」(石川県)「見島(みしま)のカセドリ」(佐賀県)「悪石島(あくせきじま)のボゼ」(鹿児島県)「宮古島のパーントゥ」(沖縄県)からも、いくつかの行事が紹介されたが、いずれも「ユネスコ無形文化遺産」効果で、地元の中学生などが後継者候補に名乗りをあげるようになったという。
これら民俗行事は、すでに国の重要無形民俗文化財に指定され、さまざまな保護を受けているが、正月のテレビ番組で紹介された「男鹿のナマハゲ」のように、生活の近代化にともなう「祭り(行事)」と「暮らし(衣食住の変化)」との乖離が進んだ結果、季節のアトラクション(観光資源としての祭り)、あるいは絶滅危惧種(昔はこんな祭りがあったそうな)の保存装置でしかなくなりつつある。その地域独特の方言は標準語(東京語)に席巻され、かつての農耕社会はグローバル化の津波に押し流されてしまった。
元来、日本人が新年を迎えるためのキーワードは「来訪神(年に一度、決まった時期に訪れるとされる神)」である。昨秋、ユネスコ無形文化遺産に登録されたこれらの民俗行事全体のタイトルに「来訪神:仮面・仮装の神々」とあるように、その祭りの多くは正月や小正月、2月初旬に行われている。
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまりの日本語――きこゆ・うたふ・かたる・つたふ「オノマト
連載 2024-03-26
-
連載「つたえること・つたわる...
ゆかいな日本語――逆さことば、しりとり、あたまとりをたのしむ
連載 2024-02-27
-
連載「つたえること・つたわる...
気になる日本語――同音異義語、異字同訓をダジャレ、謎かけであ
連載 2024-02-13
-
連載「つたえること・つたわる...
地名――大地に記された〈あしあと〉、語り継がれる〈ものがたり
連載 2024-01-23
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまり:由来→これまで:変遷→いま:現在→これから:将来。
連載 2024-01-09
-
連載「つたえること・つたわる...
エンゼルス(天使たち)から、ドジャース(ブルックリンの子ら)
連載 2023-12-26
-
連載「つたえること・つたわる...
「かなしみ」によりそう、「おもい」のちから。「大悲」は風のご
連載 2023-12-13
-
連載「つたえること・つたわる...
花びらは散る、花は散らない。散らない花を生きる。認知症の人の
連載 2023-11-29
-
連載「つたえること・つたわる...
「認知症の患者」ではない、「認知症の人」との超コミュニケーシ
連載 2023-11-14