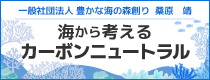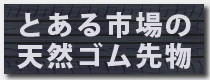連載「つたえること・つたわるもの」(27)
ほどよい間合いをとり、情報の共有化をはかる。
連載 2017-10-24
出版ジャーナリスト 原山建郎
あなたが、もし飲食店などで「相席でもよろしいですか?」と聞かれて、そこが四人掛けテーブルで、先客が左奥に座っていれば、ふつうは右手前の席に座る。わざわざ先客の隣や正面の席に座る人はいない。
肘が触れる、荷物が当たるなどのトラブルが起こらないように、また、直接目を合わせずにすむように考えて、最も遠いポジショニングをとるはずだ。電車のロングシート(横長座席)の場合なら、七人掛けなら真ん中、または両端の席を好んで座るというのも、同じような心理が働く。
つまり、相手とのちょうどよい物理的かつ心理的な距離(ほどよい間合い)をはかり、真正面からのアイコンタクトを極力避けるポジショニング(位置どり)を選択する。これは、二人の間に「ある一定の距離」を置く、あるいはお互いの視線を外すために「斜めの席」をとる、いわば安心を得るための保険(戦術)でもある。別の言い方をすれば、他人の干渉を極力受けずにすむ、目に見えない縄張りを張って、安心の領域(テリトリー)を築こうとする。
喫茶店のテーブルには、シュガーポットや紙ナプキンなどが、真ん中(二人の中間地点)に用意されている。二人の前には、まずコップ(水)が置かれる。真ん中のシュガーポットを国境として、手前がこっちの領土(ヒア)、向こうがあっちの領土(ゼア)、コップの手前の領域はそれぞれの陣地と考えることができます。中間の非武装地帯(セイフティ・ゾーン)にあるシュガーポットや紙ナプキンは、交互に利用するためのものだから、何の問題も起こらない。しかし、あっちの陣地にあるコップに手を伸ばせば、相手はムッとして険悪な表情となり、しまいには怒り出してしまうかもしれない。
エドワード・ホール(文化人類学者)は、相手との関係と距離感を四つに分類している。
①密接距離(インティメイト・ディスタンス)=0~45センチメートル。容易に相手の身体に触れることができる距離。家族、恋人などごく親しい人だけ近づける空間距離。
②個体距離(パーソナル・ディスタンス)=45~120センチメートル。二人が手を伸ばせば届く距離(エルボー・ディスタンス)。相手の表情が読みとれる空間距離。
③社会距離(ソーシャル・ディスタンス)=120~350センチメートル。身体に触れることができない距離。冠婚葬祭など改まった場やビジネスシーンで接するときの距離。
④公衆距離(パブリック・ディスタンス)=350センチメートル以上。講演会や公式な場など、個人的なつながりのない人と接するときに、複数の相手が見渡せる空間距離。
明治大学教授の齋藤孝さんは、『会議革命』(PHP研究所、2002年)の中で、「意味(情報)や感情(思い)」が効率的に〈伝わる〉戦術として、直角二等辺三角形と円卓会議のポジショニング(位置どり)を紹介している。よいコミュニケーションをはかるには、「打てば響く」ということばもあるように、お互いに響き合う身体が求められる。二人で話しているときに、二つの身体が一つの響きで充たされる、あるいは二つの身体が一つのリズムを共有できるような関係をつくること、それが〈伝わる〉戦術の基本だという。
同書から、直角二等辺三角形のポジショニング、円卓会議のポジショニングについて、要約して紹介する。
☆直角二等辺三角形のポジショニング
二人が向き合う正面のポジショニングではなく、それぞれ机のコーナーに座り、斜めのポジショニングで話すやり方。机上に資料を置くと、ちょうど二人で見やすくなる。正面に座ると、資料が同時には見にくい。
このポジショニングでは、机上の資料の中心に対してまっすぐ向き、相手に対しては資料との角度で45度になる。すると、二人の意識は、共通の土俵である資料やシートに向けられる。そのときに斜めのポジションにいる相手はもちろん意識(視野)に入っているが、この角度であれば相手を意識しすぎることはない。
☆円卓会議のポジショニング
営業会議、企画会議など、ディスカッションのとき、会議の参加者に均等に意識(アイコンタクト)を振り分けることは意外に難しい。たとえば8人の会議メンバーの場合、ほかの7人に対して7分の1ずつ意識を振り向けるのは、意外に難しいものがある。しかも、意識を振り向けられなかった人は、その人の話に対して本当には気持ちは乗っていけない。だからこそ、相互に意識をきちんと振り分ける必要がある。よいディスカッションを行うための条件は「対角線」の数を増やすことである。対角線の数は、意識の数である。
アイコンタクトができる位置であることが、意識の対角線が張られるための条件となる。横長のテーブルに長細く座る(宮中御前会議)ポジショニングでは、全員にアイコンタクトが取りづらく、均等な対角線が作れない。真中の人には、端の人が視界に入らず、どうしても近い相手と遠い相手とができてしまう。
そこで、テーブルを円卓(楕円形・円形)会議ポジショニングに変更すれば、たとえば8人の会議であれば、正三角形のそれぞれのメンバーから、均等な対角線(アイコンタクト)を引くことができる。つまり、すべての会議メンバーとアイコンタクトができ、会議中の表情、仕草も共有することが可能になるのだ。
ディスカッションの場は、メンバー一人ひとりが身体感覚で共感し、スパークするフィールドなのだ。
【プロフィール】
原山 建郎(はらやま たつろう)
出版ジャーナリスト・武蔵野大学仏教文化研究所研究員・日本東方医学会学術委員
1946年長野県生まれ。1968年早稲田大学第一商学部卒業後、㈱主婦の友社入社。『主婦の友』、『アイ』、『わたしの健康』等の雑誌記者としてキャリアを積み、1984~1990年まで『わたしの健康』(現在は『健康』)編集長。1996~1999年まで取締役(編集・制作担当)。2003年よりフリー・ジャーナリストとして、本格的な執筆・講演および出版プロデュース活動に入る。
2016年3月まで、武蔵野大学文学部非常勤講師、文教大学情報学部非常勤講師。専門分野はコミュニケーション論、和語でとらえる仏教的身体論など。
おもな著書に『からだのメッセージを聴く』(集英社文庫・2001年)、『「米百俵」の精神(こころ)』(主婦の友社・2001年)、『身心やわらか健康法』(光文社カッパブックス・2002年)、『最新・最強のサプリメント大事典』(昭文社・2004年)などがある。
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまりの日本語――きこゆ・うたふ・かたる・つたふ「オノマト
連載 2024-03-26
-
連載「つたえること・つたわる...
ゆかいな日本語――逆さことば、しりとり、あたまとりをたのしむ
連載 2024-02-27
-
連載「つたえること・つたわる...
気になる日本語――同音異義語、異字同訓をダジャレ、謎かけであ
連載 2024-02-13
-
連載「つたえること・つたわる...
地名――大地に記された〈あしあと〉、語り継がれる〈ものがたり
連載 2024-01-23
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまり:由来→これまで:変遷→いま:現在→これから:将来。
連載 2024-01-09
-
連載「つたえること・つたわる...
エンゼルス(天使たち)から、ドジャース(ブルックリンの子ら)
連載 2023-12-26
-
連載「つたえること・つたわる...
「かなしみ」によりそう、「おもい」のちから。「大悲」は風のご
連載 2023-12-13
-
連載「つたえること・つたわる...
花びらは散る、花は散らない。散らない花を生きる。認知症の人の
連載 2023-11-29
-
連載「つたえること・つたわる...
「認知症の患者」ではない、「認知症の人」との超コミュニケーシ
連載 2023-11-14