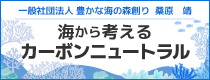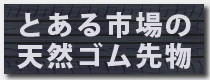連載コラム「ゴム業界の常識・非常識」④
米国ではスタッドレスタイヤはあまり使わない?
連載 2017-04-05

北米で販売しているスノータイヤ。左がグッドイヤーのUltra Grip Ice、右がブリヂストンのBlizzak WS80
加藤事務所代表取締役社長 加藤進一
日本では雪道にはスタッドレスタイヤやチェーンは当たり前です。その昔はスパイクタイヤが使われていましたが、道路表面を削り粉塵をまき散らすため、スパイクタイヤは使用禁止になりました。スタッドレスの「スタッド」とはスパイクのことです。スパイクがないタイヤで、スタッドレスタイヤという意味になります。
米国、カナダでは緯度からみると、北部は北海道のあたりと同じ気候になり、冬は雪が積もり、気温は普通にマイナス10度ぐらいになります。しかしスタッドレスタイヤはあまり使われていません。「オールシーズンタイヤ」が使われます。名前のとおり、夏でも冬でも使えるタイヤです。オールシーズンタイヤのカタログを見ると、少々の冬季の道(雪道)での走行可能と書かれています。また道路交通法でも雪道にスタッドレス、スノータイヤの使用は義務づけられていません。冬でも雪道で、チェーンを巻くことなく、そのまま走ります。では滑らないかというとやはり滑ります。また一部の州では(雪の深い地域)ではスパイクやタイヤチェーンの使用が認められています。それ以外では使用禁止です。
どうしてスタッドレスタイヤではなく、オールシーズンタイヤが使われるか?北米では雪が降ると、高速道路をはじめ、役所の道路局が道路に融雪剤を撒きます。塩化カルシウムの粒です。これで雪は解けます。そこで普通のタイヤで高速走行ができます。
しかし吹雪や、豪雪になると、この融雪剤の散布が間に合わず、雪道を通常のタイヤで走ることになります。のろのろ走るわけですが、滑ります。一時停止でブレーキを踏むと滑って止まらないことになります。それでもみんなオールシーズンタイヤで走ります。
私も米国オハイオ州アクロン市に駐在時に大雪や、ブラックアイスバーン(雪が解けてその水が氷になり、路面が黒く光る状態になり、アイススケート場で車を運転するようなもので大変危険です)で、車を滑らした経験があります。時速80キロで走りながら車を進行させながら、道の上で車を360度回転させたことがあります。最後は道脇に落ちましたが、脇が砂利だったので車が止まり助かりました。この日は高速道路のあちこちに数十台の車が路肩から落ちて脇に突っ込んでいました。
世界的にはスタッドレスタイヤ、ウインタータイヤ、スノータイヤを製造販売しているタイヤ会社は日本のタイヤメーカーの他には、ヨーロッパのミシュラン、コンチネンタルタイヤ、ピレリ、さらに米国のグッドイヤー、韓国のハンコックタイヤ等があります。これらの会社は柔らかいゴムコンパウンドを使い、さらにタイヤトレッドの形状が、雪が解けた水を素早く排出し、雪に噛んでタイヤが滑りにくいようにしています。大手タイヤ会社はそのゴムコンパウンドに工夫があります。低温でも柔らかく雪道に追従してタイヤの表面が雪をつかみます。またゴムコンパウンドの中に雪をつかむ爪のような材料を入れる場合もあります。中国製のスタッドレスタイヤもあるそうですがこれは、タイヤトレッドの形状だけ真似をして、ゴムコンパウンドの配合の工夫はしていないように見えます。形だけ真似したということです。
米国でもブリヂストン、横浜ゴムがスタッドレスタイヤを販売していますが、アメリカ人はあまり買いません。タイヤの減りが早いので、オールシーズンタイヤで十分だというわけです。噂では日本人駐在員がこのスタッドレスタイヤを買っているという話もあります。またタイヤをスタッドレスタイヤに履き替えることが面倒くさいからという理由もあります。ほとんどのアメリカ人は自分でタイヤ交換ができません。やったこともありません。自動車学校(ほとんど人は自動車学校に行きませんが)でも教えてくれません。
融雪剤を撒くと、道路が傷みます。ひびが入りやすくなります。春になるとあちこちで道路修理をしています。また州によっては道路のアスファルトにゴム粉をいれてひびがはいらないように規制しているところもあります。また塩化カルシウムを道に撒くため、自動車の底がさびやすくなります。そのため、雪が降り、雪がやむと、みんな車を自動洗車場にもっていき、アンダーシャシーバス、アンダービークルワッシュと言って、オプション費用を払い、車の下から温水をかけて、付着した融雪剤を洗い流します。さもないと車が底板から腐ってしまいます。最近は耐久性があがりましたが、まだ気にする人も多いです。
これはもう、その国の文化かもしれません。まあ融雪剤を撒くので、そのうち雪が解けるから待てばいいということかもしれません。日本では当たり前のスタッドレスタイヤ、チェーン装着は北米ではほとんどないのです。考え方の違い、いままでの歴史かもしれません。
-
連載コラム「ゴム業界の常識・...
タイヤの製造方法
連載 2023-10-04
-
連載コラム「ゴム業界の常識・...
フッ素ゴムが製造、使用ができなくなる?
連載 2023-08-08
-
連載コラム「ゴム業界の常識・...
中国でのEV車は日本のゴム会社にとってマイナスか?
連載 2023-06-07
-
連載「ゴム業界の常識・非常識...
ゴム業界で注目されるサステナブルな材料、製法
連載 2023-04-04
-
連載「ゴム業界の常識・非常識...
天然ゴムの国内価格が上がると、合成ゴムの国内価格が上がる?
連載 2023-02-13
-
連載「ゴム業界の常識・非常識...
飛行機のタイヤではどのタイヤが一番酷な使い方をされるのか?
連載 2022-12-19
-
連載「ゴム業界の常識・非常識...
インドのゴム人はマスクをしていなかった
連載 2022-10-11
-
連載コラム「ゴム業界の常識・...
アメリカのゴム人は新型コロナのマスクをしていなかった
連載 2022-08-18
-
連載コラム[ゴム業界の常識・...
世界はどんなゴム技術に注目しているのか?
連載 2022-06-06