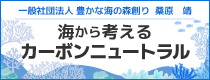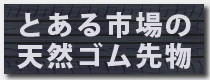連載「つたえること・つたわるもの」(40)
耳で聞いた「話しことば」を、目で読む「話しことば」にする。
連載 2018-05-08
出版ジャーナリスト 原山建郎
先ごろ、ある学会の講演とシンポジウム(公開討論)のテープ起こし(※近年は磁気テープではなく、ICレコーダーの録音再生)文字データ=実際に耳で聞いた「話しことば」から、講演録の原案=文章化して目で読む「話しことば」へのリライト作業を担当した。もちろん、このテキストデータは、講演の演者や、シンポジストの方々に発言内容のチェックをお願いするための「講演録の原案」である。したがって、実際の「話しことば」をそのまま起こした文字データも、演者の最終原稿作成の比較資料として添付した。
今回のリライト作業は、もちろん「文章の書き換え」ではない。学会誌に掲載する原稿は「講演内容の記録」が目的だから、演者が講演でとり上げた話題を追いながら、話された順番(時系列)に並べていく。耳で聞いた「話しことば」から、「てにをは(助詞)」の調整、接続詞(順接、逆接)の確認、敬体(です・ます調)と常体(だ・である調)のバランス調整など、全体の文脈を見ながら講演録の体裁をととのえる。
ところが、耳で聞いた「話しことば」は往々にして、一つのセンテンスが長くなる傾向がある。そのセンテンスの中でどれが主語でどれが述語か、目的語はどこにあるか、形容詞や副詞はどの言葉にかかるのかなど、演者がいちばん伝えたいこと、重要な「論旨」が迷子になりやすい。いくつもの短いセンテンスを、その都度完結させずに、「~ですけれども」「~なので」などの逆接・順接の接続詞で次々につないでいくと、センテンスが長くなる。これを目で読む「話しことば」にするときは、「です。しかし~」「です。したがって~」といったん完結し、新たなセンテンスを起こすほうが、伝えたい「論旨」がより明確になる。
しかし、これをやりすぎると、伝える「意味(情報)」ははっきりするが、演者の「感情(思い)」は伝わりにくくなりやすい。その理由は、聴衆が実際に耳で聞いた「話しことば」には、演者の肉声、話のテンポやリズム、感情の抑揚、演者の身振り手振り、表情の変化なども、講演全体の評価に含まれるからだ。そこで、「~ですけれども」をそのまま活かす、つまり手を加えないリライト(?)がよい場合もある。
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまりの日本語――きこゆ・うたふ・かたる・つたふ「オノマト
連載 2024-03-26
-
連載「つたえること・つたわる...
ゆかいな日本語――逆さことば、しりとり、あたまとりをたのしむ
連載 2024-02-27
-
連載「つたえること・つたわる...
気になる日本語――同音異義語、異字同訓をダジャレ、謎かけであ
連載 2024-02-13
-
連載「つたえること・つたわる...
地名――大地に記された〈あしあと〉、語り継がれる〈ものがたり
連載 2024-01-23
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまり:由来→これまで:変遷→いま:現在→これから:将来。
連載 2024-01-09
-
連載「つたえること・つたわる...
エンゼルス(天使たち)から、ドジャース(ブルックリンの子ら)
連載 2023-12-26
-
連載「つたえること・つたわる...
「かなしみ」によりそう、「おもい」のちから。「大悲」は風のご
連載 2023-12-13
-
連載「つたえること・つたわる...
花びらは散る、花は散らない。散らない花を生きる。認知症の人の
連載 2023-11-29
-
連載「つたえること・つたわる...
「認知症の患者」ではない、「認知症の人」との超コミュニケーシ
連載 2023-11-14