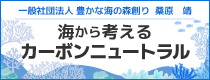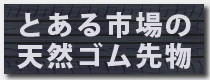連載「つたえること・つたわるもの」(45)
和製漢語・和製英語のフィーリング、現代中国の「簡体字」感覚。
連載 2018-07-24
出版ジャーナリスト 原山建郎
「日本人は外来のコード(記号、慣例)を内生のモード(様式)に転換することが得意だが、それは単なる加工技術ではなく、編集力である」とは、編集工学の泰斗、松岡正剛さんの持論。『ウェブ電通報』(2015/01/15)の対談「新・日本力の鍛え方」№4に、松岡さんの解説を見つけた。
例えば、古代日本に漢字というコードが中国からやって来たときは、それを使いこなせるプロをつくったわけですね。やがて漢詩を読める人も多く出てきて、菅原道真のように自分で漢詩をつくる人も登場する。だけど、日本のコモンランゲージ(※標準的な共通語)の方は、中国語化はしなかった。そうして、和語に当てはめて万葉仮名をつくった。また漢字から平仮名やカタカナをつくり、漢字仮名交じりという独特のモードにしました。
5~6世紀ごろ、文明大国・中国から朝鮮半島経由で日本に文字(漢字)が伝わると、日本人は「和魂漢才」を発揮して、漢文をそのまま中国語(白文)として読むだけでなく、訓点(返り点、読み仮名、句読点)をつけて読む「漢文訓読(日本語の語順に合わせて、日本語として読む)」の手法を編み出した。
日本独自の漢字(国字)もたくさん作られた。𠘨(かぜかんむり)を用いた国字には、凪(なぎ=風が止まって穏やかな状態)、凩(こがらし=冬の風が木に吹きつける)、凧(たこ=凧揚げの布が風で揺れる)がある。冬の季節感をあらわす雪を旁(つくり)に用いた、轌(そり)、鱈(たら)もある。卡(そう)を用いた国字には、裃(かみしも=肩衣+袴)、峠(たうげ=山の鞍部、上りと下りの接点)がある。
ちなみに、現在の中国では日本の「カラオケ」(中国では外来語)の発音を、同じ音の漢字を当てて表す(音写)のに、卡の音韻(カ)を用いて、「卡(カ)拉(ラ)OK(オケ)」と書く。
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまりの日本語――きこゆ・うたふ・かたる・つたふ「オノマト
連載 2024-03-26
-
連載「つたえること・つたわる...
ゆかいな日本語――逆さことば、しりとり、あたまとりをたのしむ
連載 2024-02-27
-
連載「つたえること・つたわる...
気になる日本語――同音異義語、異字同訓をダジャレ、謎かけであ
連載 2024-02-13
-
連載「つたえること・つたわる...
地名――大地に記された〈あしあと〉、語り継がれる〈ものがたり
連載 2024-01-23
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまり:由来→これまで:変遷→いま:現在→これから:将来。
連載 2024-01-09
-
連載「つたえること・つたわる...
エンゼルス(天使たち)から、ドジャース(ブルックリンの子ら)
連載 2023-12-26
-
連載「つたえること・つたわる...
「かなしみ」によりそう、「おもい」のちから。「大悲」は風のご
連載 2023-12-13
-
連載「つたえること・つたわる...
花びらは散る、花は散らない。散らない花を生きる。認知症の人の
連載 2023-11-29
-
連載「つたえること・つたわる...
「認知症の患者」ではない、「認知症の人」との超コミュニケーシ
連載 2023-11-14