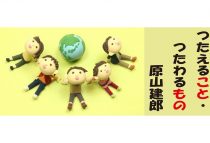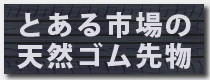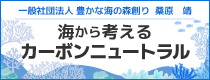連載「つたえること・つたわるもの」延長戦1
「生」から「死」へー自然体で旅立つ〈いのち〉の「間(あはひ)」。
連載 2024-06-06
出版ジャーナリスト 原山建郎
少し前のトピック(話題)になるが、2月23日(天皇誕生日)午後に開かれた中原寺(市川市、浄土真宗本願寺派)壮年会法座のあと、婦人会有志と一緒に、『在宅医療のリアル 改訂版』(幻冬舎、2019年)の著書もある上田医院院長・上田聡(うえだ そう)医師から、「在宅医療」の現状と課題についてキーノートスピーチ(話題提供)があった。
上田医院には、内科、呼吸器科など一般外来、在宅診療科(往診)のほか、訪問看護ステーション・デイケア・デイサービス「すみれ」、有料老人ホーム「我が家 中国分」が併設されている。日々の医療・介護ケアを紹介しながら、「人生の集大成である終末期をどうすごすか。在宅介護、在宅診療など、医療とのかかわり」/「笑顔、会話のある介護施設を選びたい」/「トイレ(排泄)をどうするか――「在宅医療のリアル」について話された。
身の回りのことがうまくできなくなった高齢者は、しばらくは自宅でガンバっていても、やがて高齢者の介護施設に行く、あるいは(意に反して)入れられることになる。
そのきっかけの多くは、持病(慢性病)の治療や精密検査のため、病院に入院する→持病の治療がうまくいかないと、寝たきりになる→認知症になる→家に帰れなくなる。高齢者本人は家に帰りたい・家にいたい―どうしたらよいか? たとえば、身体が弱ってくると、トイレに行きにくくなる。介助してくれる家族がいれば、パッドを入れてくれる→トイレに行けなくなるとオムツをするようになる→高齢者のプライドは大きく傷つくが、一方では介助者の負担が大きくなる→そして老人ホーム(高齢者介護施設)に行くことになる。
上田さんは、著書『在宅医療のリアル 改訂版』のなかで、第一選択:医療施設(病院)、第二選択:介護施設(老人ホーム)、そして第三選択:第3の医療としての「在宅医療」についてふれている。少し長い引用になるが、ここには重要な指摘が含まれている。
増大する医療費に頭を悩ませた国は、終末期間近にかかる医療費を減らすため、「病院にむやみに入院させないようにしよう」と考えた。病院のベッド数を大幅に削減し、入院日数を著しく制限して退院を促した。入院を長引かせると病院側の利益が減らされるようになった。急性期医療を終えた患者たちの行くところは、数少ないリハビリ病院か慢性期病院(※長期療養病床のある医療施設)。残りの大多数は介護施設に流れていった。無事に自宅に帰ることができた患者たちは、今度は大病院の外来に殺到した。一人で行くことができない人は家族やヘルパーが連れていく。介護タクシーの寝台という方法もある。何かあったらすぐに入院させてもらえることを期待する。たとえ3時間待ちの3分診療でも仕方がない。
家での生活が厳しいと判断した家族は、親を介護施設に入れる(中略)
巷に溢れた患者さんたちの受け皿になる、第3の医療としての「在宅医療」に注目が集まっているという。国が率先して推し進めているようにも見えるが、それはあくまで溢れた人たちが心配しないようにするために、第3の選択肢として用意しているだけだ。(中略)
しかし、医療費削減のために、病院で終末期を迎えると費用がかかるから、在宅の方が「安い」という誘導の仕方では、世間は変わらなかった。いざとなったら病院へ、何かあったら病院への流れは変わらなかったのだ。
近年、訪問診療は非常に充実したが、在宅での看取り件数は残念ながら伸びていない現実がある。在宅で本当の終末を迎えさせることを「よいこと」だと思っていないのが医療者の本音のようだ。実際の在宅医療の現場で「急変したら救急車を呼んで病院を受診してください」と堂々と書面で患者さんに渡しているのが何よりの証拠である。急に容態が変わったとき、もし救命できるのなら病院に行って救命してもらうという、「命救ってなんぼ」の医療観に在宅医療の現場も支配されているようだ。
在宅で何とかギリギリで頑張っている人の救命は、延命期間1日か、長くても数日の世界である。実際はほとんど助からない。
であるなら、「腹をくくって、最期を見届けよう」と僕なら思う。在宅の「何か」とは、最後の問題なのだ。
(『在宅医療のリアル 改訂版』第1章「日本の医療・介護の問題点」17~21ページ)
また、携帯電話は便利なコミュニケーション手段だが、認知症が進んだ高齢者は、多いときに一日数
菅山さんの娘さん、玉子さんは毎日何十回と母からの携帯電話を受けていた。「今日はいつ来るの?」「もう今日会ったでしょ」「あれそうだっけ」このやりとりが何十回も繰り返された。菅山さんにはいわゆる短期記憶がほぼ消失していた。一人暮らしでなんとか頑張ってきた。まだ歩けるし、自分のことは何とかできる。しかし、娘さんが音を上げたのは、毎日何十回もかかってくる電話が原因だった。
公子さんもそうだ。公子さんの場合は家の固定電話からうちの訪問看護に「背中がかゆいから来てくれ」「痛い」など、いろんな訴えを言ってくる。行ってみると何気ない顔をして、いつものベッドに座って過ごしている。来てみたら横にヘルパーがいることもある。安心電話を押すとヘルパーが飛んでくるからだ。ベッドの脇にある安心電話は、ベッドに本人がいなければまず押せない。転んでしまうと電話まで手が届かない。だからベッドにいるときに押す。ヘルパーが来てもやることがないのでそのまま引き返す。そんな日々が続いている。(中略)
挙げ出したらきりがないが、便利な電話や(※ナース)コールが、ヘルパーや看護師、そして家族を疲弊させる凶器になるのが定番だ。そして次なる処置は、携帯電話の取り上げ、コールの取り上げ、ということになる。(中略)これがなかなか大変だ。「(※有料老人ホーム)我が家」に入居した菅山さんは毎日、毎時間、毎分、いや毎秒ではないが、スタッフを呼び止め、「困りました、大変です、携帯電話がないんです」と声をかける。その都度「あー、それは玉子さんが持って帰りましたよ」とか、「壊れたから修理中ですよ」とか言って、なんとかその場をしのぐ。そこで大切なのは、つっけんどんにしないことだ。ついつい面倒くさくなると、人間はつっけんどんになってしまうが、ここが踏ん張りどころだ。そしてそこで必ず付け加える言葉は「でも、大丈夫ですよ。我々、玉子さんからよく聞いておりますので、安心してください」だ。そして、菅山さんはまた自分の部屋に帰っていく。あるいはリビングのイスに腰かける。
(『在宅医療のリアル 改訂版』第4章「介護業界のリアル」85~89ページ)
さきに、【「腹をくくって、最期を見届けよう」と僕なら思う。在宅の「何か」とは、最後の問題なのだ。】という覚悟、在宅医療が担うべきミッション(役割)を紹介したが、上田さんはさらに、最終的に渡すのは単なる「死亡診断書」ではない、とくに在宅主治医が渡すのは「大往生」という「この世の卒業証書」であると述べている。(※太字表示は原山)
いろいろ語ってきたが、この地域包括ケアシステムの中では、やはり主治医が理念的な中心となるべきだと僕は思う。病院主治医と在宅主治医が並立していることもあるだろう。そのときは、本人がどちらに軸を置くかを決めればよい。最終的には「死亡診断書」という、この世の卒業証書を渡す役割を担うのは僕らなのだから、僕らが中心になるべきだと思う。
他の人たちに勝手なことを言われて、迷って、あっちこっちに行って、めちゃくちゃになった挙げ句に亡くなって、「はい、先生書いて」といわれて書くような、残務処理的な経過報告書にはしたくない。「大往生」という立派な卒業証書を渡すには、その最期のプロセス(過程)を自分の手でよいものにしたいと思う。これが僕の目指す医療の理念である。
主治医は最終的には一人が理想だ。様々な病気を抱え、あらゆる専門家からいろんな薬を処方されてきたとして、その薬の整理をするのは在宅主治医の役目だ。目薬の止め時、骨粗鬆症の薬の止め時、高血圧薬の止め時、コレステロール薬の止め時、前立腺がんの薬の止め時、抗がん剤の止め時、これを決めるのが仕事だ。専門家集団で在宅医療を回すと、薬は止められない。
(『在宅医療のリアル 改訂版』第7章「これからの医療の形、私論在宅医療論」160ページ)
「この世の卒業証書」といえば、甲府市の在宅ホスピス医、内藤いづみさんも、「山梨のふじ内科クリニック院長のホームページ」にアップしたエッセイ、「2023年最後の看取り」のなかで、やはり「死亡診断書」ではなく「この人生の卒業証書」だと表現している。
101歳のいのちを見送りました。たぶん2023年最後の看取り。家で看取れて良かった。みんなに自慢したくなるような安らかで美しいお顔です。
私たちはみな安堵しました。頑張って母に寄り添ってきた娘さんは清清しい気持ちです、と。こんな想いを抱けるなんて当初は想像できませんでした、と虹のような笑顔でした。
死亡診断書、いえこの人生の卒業証書をお渡しした、かえり道では登る朝日に照らされました。美しかったです。
体が冷えたので、近所のデニーズでモーニングセットをひとりで食べてひと息ついてます。
ひとりのいのちを送るのにこんなに多くの人のエネルギーが必要なのに、戦争ではあっという間にたくさんのいのちを抹殺してしまう。
私はささやかな平和活動をしているんだな~と実感します。
ひと粒の種。ひとつのいのち✨
(「山梨のふじ内科クリニック院長のホームページ」「エッセイ」2023年12月31日)
「九死に一生を得る」ということばがある。「十のうち九まで死ぬと思われていたなかで、やっとのことで生きながらえること」で、いわば「救命」の意味をもつことばである。
これを「救死に永生(滅びないいのち)を得る」ということばに置き換えてみる。自然な死(ナチュラル・ダイイング)を迎えようとする〈いのち〉にとって、間もなく安らかな死を迎えるはずのタイミングで、心臓マッサージ、水分補給や昇圧剤の点滴、気管挿管などの「救命処置」は、ほんとうに必要な「手助け」なのだろうか? 人生の終末期には「救命」よりもむしろ、安らかに死を迎えるための「救死」が必要なのではないだろうか。
かつて、病院の勤務医だったころの上田さんにとっては、患者の「救命」が当たり前で、患者の「死」に対しては敗北感があった。しかし、8年前に開業した現在の上田医院で、地域の在宅医療に携わるようになって、それまでの思考回路が一変した。それは、在宅医療の現場で「自然に逝く人たち」を大勢看てきて、家族も医療者(在宅医療スタッフ全員)が「看取らせてもらった」ことによる。そこには敗北感のかけらもない、と上田さんはいう。
そして、「生」から「死」へと舵を切る準備段階、自然体で旅立つ過程(ナチュラル・ダイイング・プロセス)には、「間」が必要だとも。この「間」は単なる「あいだ/ま」ではない。上古代の日本語、やまとことばで「あはひ(間)」と読ませる。「事と事との時間的なあいだ。物と物との空間的なあいだ。人と人とのあいだがら、相互の関係。」を意味することばで、「こちら(生)」の世界(此岸)から「あちら(死)」の世界(彼岸)に、少しずつ、あるいは一気にジャンプするまでの、とてもとても「大切な時間」なのである。
自然体で旅立つために必要な「間」
肺がん末期と宣告された高橋さんは、身長180cmを超える大きな体をしていた。建設関係の仕事をしていたと言っていた。小柄な奥さんと二人暮らしだった。
僕が訪問に携わったときは、ベッドで過ごす時間が長くなっていた。トイレにはベッド柵や壁を伝って何とか一人で行けていた。伺うといつも横になっていた。じっと天井を見つめていた。「よっこらせ」と足を伸ばしたまま起き上がり、挨拶をかわす。話はいつも「俺はいろんなところに行った」と壁の方に指をさす。壁に貼ってある地図にはいっぱいピンが刺されていた。
奥さんの専らの心配事は病院の先生から「高橋さんは認知症の症状が出ている」と言われたことだった。「いつしかうちの主人が徘徊して外に出ていってしまうのではないか」と心配し、背の高いご主人の「背の届かないところに鍵をつけておかないと」と背の低い奥さんは悩んでいた。「テレビで認知症になると徘徊して外にフラフラ出ていって、もどって来られないと言っていた」と奥さんは本気で悩んでいた。「啓蒙活動(※「認知症の人は徘徊行動に注意せよ」という一般的なアドバイス)の結果ってこんなもんだよね」と僕はぼやく。
しかし、奥さんの心配とは裏腹に、ご主人は何の心配もなさそうに暮らしていた。自分の置かれている状況を理性的に見ずに、本能的に暮らしていた。歩けなくなったことへの愚痴、生命が残り少なくなっていることへの恐怖、食事ができなくなっていることへの疑問などは全く聞かれなかった。
そんな高橋家の終末期の風景は自然に訪れた。寝る時間が増え、トイレにも行けなくなった。ベッドでオムツを使用した期間はわずか二日だった。
本能的に「生」から「死」の方向に「間」を置きながら舵を切りつつあるとき、大体の方はその「間」に覚悟らしきもの、そしてその「間」のおかげか自然体で向こうに行くことができてくるように見える。多くを語らず、遠くを見つめるような感覚。西を見ているのか、上を見ているのか、諦めの感情より深い何か。
そして、それは薄ら呆けた感じの雰囲気の中にも漂う。この様子について「認知症」の症状が出たという人がいるが、それは見え方が僕とは違う。生から死への舵切りの間に訪れる「呆けた」間の状態。下手をするともしかしたら皆の言う「認知症」とは、生から死へ舵を切るときのための、この世のことを忘れるための準備段階に出る必然的なものだといえるのではないか。
(『在宅医療のリアル 改訂版』「第5章「死」と「理性」」113~115ページ)
「生」と「死」の「あはひ(間)」に行き交う〈いのち〉の光、静かな火花(バイオ・スパーク)。
【プロフィール】
原山 建郎(はらやま たつろう)
出版ジャーナリスト・武蔵野大学仏教文化研究所研究員・日本東方医学会学術委員
1946年長野県生まれ。1968年早稲田大学第一商学部卒業後、㈱主婦の友社入社。『主婦の友』、『アイ』、『わたしの健康』等の雑誌記者としてキャリアを積み、1984~1990年まで『わたしの健康』(現在は『健康』)編集長。1996~1999年まで取締役(編集・制作担当)。2003年よりフリー・ジャーナリストとして、本格的な執筆・講演および出版プロデュース活動に入る。
2016年3月まで、武蔵野大学文学部非常勤講師、文教大学情報学部非常勤講師。専門分野はコミュニケーション論、和語でとらえる仏教的身体論など。
おもな著書に『からだのメッセージを聴く』(集英社文庫・2001年)、『「米百俵」の精神(こころ)』(主婦の友社・2001年)、『身心やわらか健康法』(光文社カッパブックス・2002年)、『最新・最強のサプリメント大事典』(昭文社・2004年)などがある。
-
連載「つたえること・つたわる...
〈泣いて〉生まれて〈笑って〉死ぬー〈いのち〉の臨界点をさぐる
連載 2024-06-27
-
連載「つたえること・つたわる...
書き手も読み手も癒すメディアーブック(書籍/雑誌)セラピー。
連載 2024-06-20
-
連載「つたえること・つたわる...
そのときは「家」でー〈なかよし〉時間、〈自然死〉ハイライト。
連載 2024-06-13
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまりの日本語――きこゆ・うたふ・かたる・つたふ「オノマト
連載 2024-03-26
-
連載「つたえること・つたわる...
ゆかいな日本語――逆さことば、しりとり、あたまとりをたのしむ
連載 2024-02-27
-
連載「つたえること・つたわる...
気になる日本語――同音異義語、異字同訓をダジャレ、謎かけであ
連載 2024-02-13
-
連載「つたえること・つたわる...
地名――大地に記された〈あしあと〉、語り継がれる〈ものがたり
連載 2024-01-23
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまり:由来→これまで:変遷→いま:現在→これから:将来。
連載 2024-01-09
-
連載「つたえること・つたわる...
エンゼルス(天使たち)から、ドジャース(ブルックリンの子ら)
連載 2023-12-26