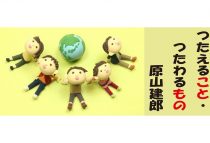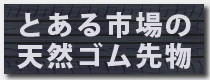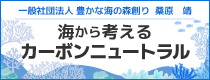連載「つたえること・つたわるもの」延長戦4
〈泣いて〉生まれて〈笑って〉死ぬー〈いのち〉の臨界点をさぐる。
連載 2024-06-27
出版ジャーナリスト 原山建郎
去る5月18日(土)午前10~12時、桜美林大学リベラルアーツ学群准教授(神学)、長谷川(間瀬)恵美さんが研究代表者である「死の受容」研究会の第12回定例研究会(Zoomミーティング)で、話題提供者(キーノートスピーカー)をつとめた。この研究会は、日本学術振興会(文部科学省所管の独立行政法人)が科学研究費を助成する「科学研究費基盤研究C(一人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究。助成期間は3~5年間)」のひとつで、『患者を看取った宗教者の「死の語り」に関する研究-宗教多元主義の理論と実践』(2022~2024年度)というタイトルの、アカデミックかつスピリチュアルな研究会である。
数カ月前、長谷川さんから「クオリティ・オブ・デス」における「〈いのち〉の臨界点」について話してほしいと依頼を受けたので、この日のテーマは、「クオリティ・オブ・デス」〈泣いて〉生まれて〈笑って〉死ぬ――〈いのち〉の臨界点(Critical point of Life)をさぐる。とした。研究会参加者へ事前に送信された案内状の「発表内容」には、次の一文を掲げた。
クオリティ・オブ・デスには、医学的な死(肉体の細胞死)だけでなく、死にゆく過程や遺族に対するグリーフ・ケアを含む広義の「死」がある。出産時に妊婦のいきみと胎児の娩出がもたらす「往相(おうそう)の呼応」があるように、「これ以上は生きられない」と告げる自然死にも「還相(げんそう)の呼応」という〈いのち〉の臨界点がある。オギャアと泣いて生まれた私たちは、笑って死ぬことができるのか。「老いる・病いる」生き方をさぐる。
少し堅苦しいタイトルになったが、この日の重要なキーワード、「〈いのち〉の臨界点」を意識しながら、80分ほど話した。そのあと約40分、参加者からの鋭い質問、示唆に富んだ意見を拝聴した。Zoomミーティングで配布したレジュメ(目次・項目)は以下の通りである。なお、各項目(1.~6.)の末尾に※をつけて、これまでの連載コラムでとり上げた号数(№)を記したので、このテーマに興味がある方は、これまでの連載コラムのバックナンバーをぜひ読み返してほしい。
1.クオリティ・オブ・デス、〈いのち〉を生きる〈死に方〉 ①なぜ、〈いのち〉を生きる〈死に方〉なのか。/②「去年(こぞ)今年(ことし)貫く棒の如きもの」高浜虚子/※№176【はじまり:由来→これまで:変遷→いま:現在→これから:将来。】
2.「泣きながら」生まれてきて、「笑いながら」死んでゆく。 ①「長い人生には、思い通りにならないこともある」/②『産声をあげるとき、息を引き取るとき』/③アメリカの哲学者、ラルフ・ウォルドー・エマーソンの言葉/④阿吽(あうん)の呼吸、〈いのち〉の始まりと終わり。/※№120【〈からだ〉をきたえる健康法から〈いのち〉をやしなう養生法へ。】
3.「往相回向・還相回向」の向きを変え、「往相の呼応・還相の呼応」で考える。 ①人の誕生を「往相の呼応」、人の往生を「還相の呼応」ととらえてみる。/②野球は「ホーム(本塁)」から出発して「ホーム(わが家)に還るゲーム。
4.緒形拳のことば。「病(やま)いる」――病いを生きる。 ①「病(やま)いる」とは「病いの人生」を生き切る、まっとうすること。/②生まれることと死ぬことが、〈いのち〉の臨界点でひとつになる。/※№123【病(やま)いる、生まれる・死ぬ〈いのち〉の臨界点。】
5.ターミナル期の「患者」と、その「家族」の戸惑いと悩み。 ①「奥さんは部屋から出てください」/②「安楽死」で死なせて下さい』/③安楽死、尊厳死、自然(しぜん)死、自然(じねん)死。/※№54&55【クオリティ・オブ・デス、リビング・ウイルを考える――その1・その2】
6.ナチュラル・ダイイング、グッド・デス(よき死)を全うする。 ①「死は不幸の完成」ではない。「グッド・ライフ」として生き切る。/②ナチュラル・ダイイング、グッド・デス(よき死)を看取る。/③救急・救命だけでなく、「救死」も大切な医療である。/④「怖がらなくてもよい」という「道しるべ」を立てる。/※№76【ナチュラル・ダイイング、自然な〈お迎え〉を阻むもの。その1】、№182【「生」から「死」へ――自然体で旅立つ〈いのち〉の「間(あはひ)」。】
Zoomミーティングでの発表を要約しながら、★「泣きながら」生まれ、「笑いながら」死んでゆく。★〈いのち〉の臨界点をさぐる。この重要な二つのトピックについて考えてみよう。実際の発表は耳で聞く「ですます調」だったが、本コラムでは目で読む「である」調に変えて記述する。スピーチの一部は割愛し、理解を助けるための短い説明を補足した。
★「泣きながら」生まれ、「笑いながら」死んでゆく。
◆生と死は、コインの表裏のようなもの
山梨県甲府市の在宅ホスピス医、ふじ内科クリニック院長の内藤いづみさんは、シニア女性誌『いきいき』に寄稿したエッセイ『産声をあげるとき、息を引き取るとき』の中で、『チベット死者の書』に書かれた経典の一節を紹介している。
生と死は、コインの表裏のようなもの。
以前、作家の遠藤周作先生からいただいた『チベット死者の書』を思い出しました。これは、死の瞬間から次の生を得て誕生するまでに魂がたどる四十九日の旅を描写した経典で、臨終を迎えた人の枕元で僧が読む習慣がチベットにはあるのだそうです。経典には、「私たちが泣きながら生まれてくるとき、周囲の人々は歓喜の声をあげる。私たちが死んでいくとき、周囲の人々は泣き、私たちは歓喜に満ちて笑う」と書かれていました。
私の患者さんの多くは、亡くなって30分くらい経つと、穏やかないい笑顔になります。
その顔を見ていると、「ああ、いいところに行ったんだなあ」と、こちらもほっとした気持ちになる。あっちの世界々は怖いところではなさそうだ、と思わせていただいています。
(『いきいき』2013年6月号)
◆ラルフ・ウォルドー・エマーソンの言葉
「心の奥底に達してあらゆる病を癒せる音楽、それは温かい言葉だ」などの名言で知られる、十九世紀に活躍したアメリカの思想家、ラルフ・ウォルドー・エマーソンの言葉。
「あなたが生まれたとき、あなたは泣いていて、みんなは微笑んでいた。 だからあなたが死ぬときは、あなたが笑って、みんなが泣くような人生を生きなさい」(When you were born you were crying and everyone else was smiling. Live your life so at the end, you’re the one who is smiling and everyone else is crying.)
◆阿吽(あうん)の呼吸
「阿吽(あうん)の呼吸」ということばがある。
一般的には「二人以上でいっしょに物事を行うときの、互いの微妙な気持ち。二人の息が合うこと」をいうが、阿(あ)は口を開いて最初に出す音、吽(うん)は口を閉じて出す最後の音。阿吽は宇宙の始まりと終わりを表す言葉である。
沖縄のシーサー(守り神の獅子)も、神社の狛犬(境内の邪気を祓う)も、向って右側が口を開けた「阿」、左側が口を閉じた「吽」である。人も阿形(あぎょう)でオギャーと口を開いて生まれ、 吽形(うんぎょう)で口を閉じて息を引き取る。人は生まれるとき、「おぎゃあ(産声)」と泣いて息を吐き、肺を浸していた羊水を吐き出して、口から息(酸素を含む空気)を肺に吸い込み、次に息(炭酸ガスを含む空気)を吐き出す――ここから肺呼吸が始まる。
★〈いのち〉の臨界点をさぐる。
◆此岸に生まれる「往相の呼応/啐啄同時」、彼岸に還る「還相の呼応/往生」
仏教では、人が亡くなる(死)ことを「往生(おうじょう)」という。人は死後、必ずお浄土(彼岸・ゼア)に「往(ゆ)」きて「生(い)」きる、わが身が救われてゆく。これを「往相(おうそう)」という。そして、さらにお浄土に行きっぱなしではなく、直ちにこの世(此岸・ヒア)に「還(かえ)」ってきて、すべてのものの苦悩を救う〈はたらき〉をする。これを「還相(げんそう」という。この世(此岸・ヒア・現住所)で暮す私たちが、死後にお浄土(彼岸・ゼア・本籍地)に救われて生きる「往相」、そして再び、この世(此岸・ヒア)に還ってきて、救いの〈はたらき〉をする「還相」というとらえ方である。
これを、逆に〈いのち〉の本籍地である「お浄土(仏のまなざし)」から見ると――仏教的な考えでは誤りであるかもしれないが、以下はあくまでも原山説—―人の誕生(出産)は、この世(此岸・ヒア・現住所)に「往」きて「生」きる「往相」=新生(New Arrival)、つまり妊婦のいきみと胎児の娩出がもたらす「往相の呼応(母親が「もういいよ、そろそろ生まれておいで」と呼びかけ、胎児がそれに答える)」であり、また人の死は「これまでよく生きた。お浄土に還っておいで」と告げる「還相の呼応(絶対者である仏の呼びかけに、私が答える)」――「新しい旅立ち(New Departure)」を介して、懐かしいお浄土(彼岸・ゼア・本籍地)に還ってゆく「還相」=「故郷への帰還(Return to Home)」である、と考えることはできないだろうか。
やはり禅の言葉に「啐啄同時(そったくどうじ)」がある。卵の中の雛が「お母さん、もうすぐ生まれるよ」と内側から殻をつつく「啐(そつ)」の音、卵の変化に気づいた親鳥が、「ここから出てきなさい」と外側から殻をつつく「啄(たく)」の音とが、ぴったり同じタイミングでシンクロする。これも「往相の呼応」といえるのではないだろうか。
◆「ホーム」から出発し、ダイヤモンドを一周、再び「ホーム」に還る。
また、たとえば、いま大谷翔平選手の大活躍で人気の野球(ベースボール/Baseball)には、4つの塁(ベース/Base)がある。1~3塁(First・Second・Third base)までは数字で数えるが、「ホームランを打った選手が戻ってくる場所」に由来する本塁(ホーム・プレート/Home Plate:ホーム・ベース/ Home Baseは和製英語)だけは、「ホーム」と呼ばれている。なるほど、「ホームラン(Homerun)」を打った選手は「ホーム」から出発して、ダイヤモンドを一周し、再び「ホーム」へ生還(Return Alive)する。本塁(ホーム)から出発する出塁と走塁は「往相」。ダイヤモンドを一周して本塁(ホーム)へ生還(帰還)する「還相」。ベースボールは、「生・老・病・死」という名の「人生ゲーム」によく似ている。
そういえば、メーテルリンクの童話『青い鳥』では、チルチル、ミチルの兄妹が、ある日家に訪ねてきた老婆に「ここに幸せの青い鳥はいないか?」と言われたことから始まる。「うちには白い鳥しかいない」と答えると、「では、青い鳥を探してきておくれ」と頼まれる。老婆からもらったダイヤモンドのついた帽子―—それを回すと魔法が起きる―—をかぶって、二人は家(ホーム)から外に出て「青い鳥」探しに出る。何度も「青い鳥」を見つけるのだが、すぐに羽の色が変わってしまう—―失意・落胆した二人が、もう一度、帽子のダイヤモンドを回してみると、あっという間に懐かしいわが家(ホーム)に戻っていた、そして「白い鳥」しかいなかった鳥籠には「幸せの青い鳥」がいた、というお話である。これは「ほんとうの幸せは、自分の外(そと・アウトサイド)に求めるのではなく、自分の内(うち・インサイド=ホーム)にあるダイヤモンド(青い鳥)に気づくこと、という物語でもある。
◆産まれること・死ぬこと――「いのちの臨界点」ということば。
上代日本人は、今までできていたことが、急に、または徐々にできなくなった「やむ(止む)」状態を、「やむ(病む)」+「まふ(耗ふ)」=「やまふ(病ふ)」→「やまひ(病ひ)」ととらえた。そして、「やまふ」という言葉を病気のことだけに限定せず、「やむ(止む)+まふ(耗ふ)」の組み合わせで考えれば、やがて死に至る病気だけでなく、いわゆる老衰(若いときはできたことが、徐々にできなくなる)や自然死(ナチュラル・ダイイング)もまた、広義の「やまひ」に含まれる概念である。2008年の連続テレビドラマ『風のガーデン』が遺作となった俳優、緒形拳さんが遺した「病(やま)いる」という言葉がある。「病いる」は「老いる」と同じ仲間で、「老いる」とは「老いをい(生)きる」ことであり、「病いる」も同じように「病いをい(生)きる」ことなのだ。「いきる」を「人生をともに生き切る」と読み替えれば、「老いの人生を受け止め、老いとともに最後まで生き切る」、「病いの人生を受け止め、病いとともに最後まで生き切る」となる。
◆「怖がらなくてもよい」という「道しるべ」を立てる。
ナチュラル・ダイイング・プロセス(自然死に至る準備過程)について書いた『看取り先生の遺言――がんで安らかな最期を迎えるために』(奥野修司著、文藝春秋、2013年)がある。遺言の主、看取り先生である、肺がん専門医の岡部健さんが、医療専門誌に寄稿した一文、『患者体験から見えるケア――在宅緩和ケアの原点に戻る――』(『緩和ケア』2011年9月号)が同書に紹介されており、そのなかに「道しるべ」ということばがある。
すでに、2019年の本コラム№77(ナチュラル・ダイイング、自然な〈お迎え〉を阻むもの。その2)で引用しているが、「〈いのち〉の臨界点」に立ちあう臨床医や看護師などベッドサイドの医療者、あるいはチャプレン(病院付き神父や牧師)や仏教僧などの臨床宗教師に求められる【「道しるべ」を立てる】意味を考える手がかりに、その一部を再掲しよう。
在宅での看取りができるかどうかは、宮沢賢治の「南二死二サウナ人アレバ 行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ」という一言をわれわれ(※医療者)が言えるかどうかにかかっています。われわれはあの一言を、本当に患者さんに言えているでしょうか。生の世界を引き延ばすはなしではなく、「怖がらなくてもよい」という道しるべを立てることができているでしょうか。地域にあった死生観を掘り起こしつつ、論理からではなく、看取りの経験の積み重ねによって、再び死の側の斜面の道しるべを立て直す時期に、今、きているのだと思います。
(『看取り先生の遺言』173ページ)
岡部さんが、この一文に引用した宮澤賢治の詩『雨ニモマケズ』は、宮澤の没後に発見された黒い手帳に青鉛筆で記された遺作のメモである。青空文庫(日本の電子書籍サービス。著作権が消滅した作品や著者が許諾した作品を、電子書籍で公開し無料で提供している)の助けを借りて『雨ニモマケズ』の全文(※/は改行を表わす)を紹介しよう。
雨ニモマケズ/風ニモマケズ雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ/丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク/決シテ瞋(イカ)ラズ/イツモシヅカニワラッテヰル
一日ニ玄米四合ト/味噌ト少シノ野菜ヲタベ
アラユルコトヲ/ジブンヲカンジョウニ入レズニ
ヨクミキキシワカリ/ソシテワスレズ
野原ノ松ノ林ノ䕃(カゲ)ノ/小サナ萓(カヤ)ブキノ小屋ニヰテ
東ニ病気ノコドモアレバ/行ッテ看病シテヤリ
西ニツカレタ母アレバ/行ッテソノ稻ノ朿ヲ負ヒ
南ニ死ニサウナ人アレバ/行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ
北ニケンクヮヤソショウガアレバ/ツマラナイカラヤメロトイヒ
ヒドリノトキハナミダヲナガシ/サムサノナツハオロオロアルキ
ミンナニデクノボートヨバレ/ホメラレモセズ/クニモサレズ
サウイフモノニ/ワタシハナリタイ
南無無辺行菩薩/南無上行菩薩/南無多宝如来/南無妙法蓮華経
南無釈迦牟尼仏/南無浄行菩薩/南無安立行菩薩
※宮澤賢治は浄土真宗(生家が代々門徒)だったが、日蓮宗に惹かれて、やがて法華経の信者になる。日蓮宗では「法華経」に登場する上行(じょうぎょう)、無辺行(むへんぎょう)、浄行(じょうぎょう)、安立行(あんりゅうぎょう)を「四菩薩」と称する。多宝如来(たほうにょらい)は、過去仏(釈尊以前に悟りを開いた無数の仏)の一人である。
3.11(2011年の東日本大震災)の直後、日本版臨床宗教師の必要性を訴えた岡部さんの願いに応えて、東北大学大学院に「実践宗教学寄附講座」が開設された。この講座が目指すものは、「怖がらなくてもよい」という「道しるべ」を立てる、あるいは示してくれる宗教者、特定の宗派にこだわらない臨床宗教師の活動であり、あるいは日本に古くから伝わる祖霊信仰とも深い関係にある。すでに亡くなった家族(祖先)からの呼びかけ、さきに述べた「還相の呼応」としての、いわゆる〈お迎え〉現象に見守られながら、穏やかで・安らかな最期を迎えるために、この「道しるべ」は、すべての人のナチュラル・ダイイング・プロセス(自然死に至る準備過程)に向けられるべき、あたたかいまなざしである。
そして最後に、この日のキーノートスピーチを、次のメッセージで締めくくった。
本日の定例研究会、『クオリティ・オブ・デス(Quality Of Death)――泣いて生まれて、笑って死ぬ――〈いのち〉の臨界点をさぐる』でとりあげた「〈死〉を迎える〈いのち〉の臨界点」とは、「これまでよく生きてきた。〈いのち〉の本籍地である〈ホーム(故郷)〉に還っておいで」と告げる「還相の呼応(絶対者の呼びかけに、私の〈いのち〉が答える)」――「故郷への帰還(Return to Home)」、あるいは「新しい旅立ち(New Departure)」に向って舵を切るための、とても大切な「転換点( Turning Point)」だと思います。
〈いのち〉が故郷に還る。新しい〈いのち〉の旅立ちに向けて舵を切る。—―とても大切な〈いのち〉の臨界点。新しく生きる〈いのち〉転換点。
【プロフィール】
原山 建郎(はらやま たつろう)
出版ジャーナリスト・武蔵野大学仏教文化研究所研究員・日本東方医学会学術委員
1946年長野県生まれ。1968年早稲田大学第一商学部卒業後、㈱主婦の友社入社。『主婦の友』、『アイ』、『わたしの健康』等の雑誌記者としてキャリアを積み、1984~1990年まで『わたしの健康』(現在は『健康』)編集長。1996~1999年まで取締役(編集・制作担当)。2003年よりフリー・ジャーナリストとして、本格的な執筆・講演および出版プロデュース活動に入る。
2016年3月まで、武蔵野大学文学部非常勤講師、文教大学情報学部非常勤講師。専門分野はコミュニケーション論、和語でとらえる仏教的身体論など。
おもな著書に『からだのメッセージを聴く』(集英社文庫・2001年)、『「米百俵」の精神(こころ)』(主婦の友社・2001年)、『身心やわらか健康法』(光文社カッパブックス・2002年)、『最新・最強のサプリメント大事典』(昭文社・2004年)などがある。
-
連載「つたえること・つたわる...
書き手も読み手も癒すメディアーブック(書籍/雑誌)セラピー。
連載 2024-06-20
-
連載「つたえること・つたわる...
そのときは「家」でー〈なかよし〉時間、〈自然死〉ハイライト。
連載 2024-06-13
-
連載「つたえること・つたわる...
「生」から「死」へー自然体で旅立つ〈いのち〉の「間(あはひ)
連載 2024-06-06
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまりの日本語――きこゆ・うたふ・かたる・つたふ「オノマト
連載 2024-03-26
-
連載「つたえること・つたわる...
ゆかいな日本語――逆さことば、しりとり、あたまとりをたのしむ
連載 2024-02-27
-
連載「つたえること・つたわる...
気になる日本語――同音異義語、異字同訓をダジャレ、謎かけであ
連載 2024-02-13
-
連載「つたえること・つたわる...
地名――大地に記された〈あしあと〉、語り継がれる〈ものがたり
連載 2024-01-23
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまり:由来→これまで:変遷→いま:現在→これから:将来。
連載 2024-01-09
-
連載「つたえること・つたわる...
エンゼルス(天使たち)から、ドジャース(ブルックリンの子ら)
連載 2023-12-26