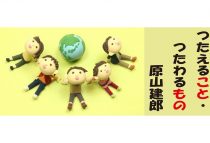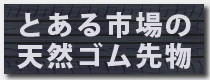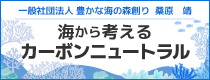連載「つたえること・つたわるもの」延長戦3
書き手も読み手も癒すメディアーブック(書籍/雑誌)セラピー。
連載 2024-06-20
出版ジャーナリスト 原山建郎
私はかつて、毎月1回(7年3カ月間)、1ページの連載コラム『ブックセラピー(book therapy)』を『出版ニュース』誌に書いていた。シリーズ名の「ブックセラピー」は、清田義昭編集長から与えられた課題、あるいは宿題のようなタイトルだった。
たとえば、「リーダー(読み手・reader)」が主語なら「この本を読むことで〈癒される〉」のかどうか―—「ブック(書き手・writer)」が主語なら「どのように読んでもらえたらうれしいか、書き手の気持ちが伝わることで〈癒される〉」のかどうか―—。
このときはもちろん、『出版ニュース』誌の主たる読者(出版社、取次、書店関係者など)を意識しながら、毎回、1冊か2冊の「ブック(書籍)」を文中に引用しつつ、『ブックセラピー』の原稿(約1500字)を書いた。また、「文中引用」の基本的ルールである「書誌情報(著者・編者名、訳者名、出版元、出版年)」と「引用ページ」を明示することで、自分自身の著書も含む「ブック≒著者」を最大限にレスペクトした。
本コラムでも遵守する「基本ルール」には、利便性が二つある。一つは、図書館の蔵書検索に必要なデータ(タイトル、著者等、出版者)がすべてあること。もう一つは、コラムの文中で引用されたトピック(話題)のページが、すぐに開けることである。
「本」を意味する英語「ブック(book)」を、インターネットの語源検索サイトで調べてみると、古英語のboc(書籍、文章、書かれた文書)に由来し、原始ゲルマン語のbokiz(ブナの木=英語はbeech)が語源だという。その昔、書物はブナの「木の皮(薄板)」に書いていたらしい。また、「本」のフランス語「リブレ(livre)」は、ラテン語のlibrum(木の内皮)に由来し、ここからlibrary(本箱→本の貯蔵→図書館)も派生している。
ちなみに、ユダヤ教やキリスト教の聖典である「聖書」は、英語ではthe bible、あるいはthe bookと呼ばれ、紙の原料となるパピルスの茎の内皮を指すギリシャ語の「ビブリア(biblia)」が語源。はじめは小冊子や書物の一部という普通名詞だったが、キリスト教会において固有名詞化し、5世紀ごろから聖書全体がビブリアと呼ばれるようになったという。
漢字の「本(ホン/もと)」の成立ちを『字通』(白川静著、平凡社、1996年)で引くと、「木の下部に肥点(※横線)を加えて、木の根元を示す」と説明されている。さらに、白川静記念東洋文字文化研究所、後藤文男研究員はブログ『ゴット先生の京都古代文字案内』(エフエム世田谷2021年10月31日放送)で、「本」は「木の根本はここだ」と示す字で、物事の「もと」、物事の「根本・根元」をいう字である、と述べている。(太字は後藤さん)
「本」という字は「木」の形からできています。本の材料の紙は木(パルプ)からできていますから、古代の人たちも木が紙の材料になることを知っていたのかと思われるかもしれませんが、「本」という漢字ができたころ(今から3000年ほど前)には「紙」はありませんでした。紙が出来るのはずっと後のこと、今から1900年ほど前の西暦100年頃の後漢の時代です。
ですから、「本」は、最初は「ほん」ではなく「もと、はじめ」という意味で用いられていました。古代文字(金文)を見ると、木の幹の根元にそこを強調するかのように膨らんだ円い部分(肥点)があります。その膨らんだ部分が、800年ほど経つと、木の根元に横棒として書かれるようになります。それが、現代の「本」の字の基になりました。
このように「本」は木の字の幹の下側に肥点を打って、木の根元はここだと表す字として生まれました。そこから、物事の「もと」=「根本(根元)」を意味する字として用いられるようになりました。その「本」が「Book」の「ほん」」の意味で用いられるようになったのは、おそらく、知識の多くは文字が書かれた書物から得たので、その書物こそ知識の「大本」だととらえたからだと思われます。書物を表す「本」は、知識の宝庫だったのです。ですから、そこに書かれていることは信じるにたるもの、「本物」、「本当」というように、「ただしい、まこと」の意味で用いられるようになりました。
(『ゴット先生の京都古代文字案内』ラジオ第170回「本」にまつわる漢字)
たとえば、音楽(歌唱、器楽演奏、音楽鑑賞)を通じて心身の安定をはかる「音楽療法(musical therapy)」がよく知られているが、「本(書籍)の」を意味するフランス語「ビブリオ(biblio)」を冠した「ビブリオセラピー(読書セラピー)」もある。日本読書療法学会(寺田真理子会長)は、これを「読書によって問題が解決したり、何らかの癒やしが得られたりすること」と定義している。つまり、これは読み手が「どのような本を読むことによって〈癒される〉か」という視点での「ブックセラピー」である。
もう一つの視点、書き手が「どのように読んでもらえたらうれしいか、書き手の気持ちが伝わることで〈癒される〉」では、このシリーズ名「つたえること・つたわるもの」に込めた、書き手が「つたえる・こと」と、読み手に「つたわる・もの」が、必ずしも一致するとはかぎらない――この場合、これまでに何冊か上梓した私自身も含めた著者(書き手)は、想定外の読まれ方に驚き、そのことを残念に思うにちがいない。
しかし、書き手の(頭の中にある)思いや主張を読み手の「誰か」に「つたえる」ために書かれた文章(原稿)は、実は「ブック(書籍/雑誌)」の形になった時点でもう「書き手」を離れ(release)、その「ブック」は読み手(読んだ人)のものになる。
「ブック」の読み手は、そこに書かれた文章を「目で追う」のではなく、読み手の〈からだ/歴史的身体(これまでの人生で味わった喜びや、悲しみの集積)〉にいったんとり入れ、ゆっくりとあるいは急いで咀嚼し、自らの〈からだ〉を構成する37兆個の体細胞のいくつかに、しっかり上書き(overwrite)されていく。「ブック」を読む前の〈からだ/歴史的身体〉と、読んだあとの〈からだ/歴史的身体〉が、ときに大きく変わることがある。
ノンフィクション作家の佐野眞一さんは、高著『だれが「本」を殺すのかPART-2 延長線』(プレジデント社、2002年)のなかで、それが「いい本」だと喝破している。
いい本というのは何か、ひと言でいえます。それは簡単です。読む前と読んだあとの世界が違って見える本がいい本です。たとえば、この机の幅が1メートルだとしますね。その1メートルの距離が3メートルに見えたり、あるいは50センチに見えたりする本、つまり世界観が変わってしまう本、これがいい本です。いい作家とは何か。時間を止めてみせることができる人間です。これを芸術家と、僕は呼ぶ。彫刻家もそうです。絵描きもそうです。音楽家もそうです。時間を一瞬止めてしまう。実際には、時間は止まらない。だけど、一種の幻想ですけれども、本を読んでいるとき、時間を止めてみせることのできる人間しか、僕は芸術家と呼べないと思います。
(『だれが「本」を殺すのかPART-2延長線』講演②流山市「ゆうゆう大学」61ページ)
さきに、「ブック」を読む前の〈からだ/歴史的身体〉に上書き(overwrite)された――「ブック」を読んだあとの〈からだ/歴史的身体〉と述べたが、「上書き(overwrite)」という言葉から、「ブック」を「読む(read)」行為は読み手の〈からだ/歴史的身体〉のなかで「ブック」を書写する(トランスクライブ:transcribe)、つまり自分が初めて出会う新しい文章を「書く(write)行為であることがわかる。
さらに別の言い方をすると、「ブック」を読むという行為は、読み手(自分)が書き手(著者)に取材(インタビュー)する行為でもある。インタビュー(interview)とは、二人の間で(inter-)お互いが見合う(view)ことだが、その取材結果が「ブック」に書かれている、と考えることはできないだろうか。もし、そうだとすれば、「読み手」である自分は、同時に「書き手(取材記者)」でもある。「ブック」を一読、再読するなかで、取材記事(=著者の文章)を頭のなかで「書いて(書写・閲読)」いるのだと、いうことになる。
「ブックセラピー」→癒す(healing)方法に、「ヒーリング・ライティング(書いて癒される)」と「ヒーリング・リーディング(読んで癒される)」とがある。
「ヒーリング・ライティング(書いて癒される)」に関する文章を中心に書いている、つなぶちようじさんは、高著『あなた自身のストーリーを書く』(主婦の友社、2002年)で、自分の過去を文章に書いてみる、「私は誰か(自分以外の視点で見る)」ことの重要性を説いている。これは、つまり「歴史的身体」と対話する有効なセラピーのひとつである。
私は誰か。知らない人はまずこの本を読んでいないでしょう。まず名前を知っている。どこに住んでいるのか知っている。両親や家族を知っている。趣味を知っている。どんな食べ物が好きかを知っている。ほかにもたくさんの自分を決定づけている要素があるはずです。つまり、いろんな自分を知っていることが、自分は誰かを決めています。それらはすべて過去の経験やできごとが基点になっています。
過去は変えようがありません。過去の集積が自分なのですから、現在の自分自身も変えようがありません。そのように考えるのが一般的でしょう。しかし、この本では過去を見つめることによって、現在の自分をつくりかえる方法を提示していきます。「つくりかえる」というと、少し表現がおおげさかもしれません。自分の心の表情を変えてみるというのがいいでしょう。(中略)表情というのは自由に変えているようで、あまり自由にはなりません。無理に笑おうとするとひきつってしまいますし、泣こうとしても簡単に涙は出ません。それと同じに心の表情も変えようとすればするほど硬直していきます。「気分を明るくしよう」とか「いまは悲しいのだからしかたない」などのように、自分のことを自分以外からの視点で見るようなことを考えると、案外気が晴れたりします。
それと同様に、自分の過去を文章にすることによって、あたかもだれかのお話を小説やエッセーにでも書いているように表現していくと、不思議と気分が落ち着いていきます。
また、自分は誰であるかを突き詰めていくと、最後には「誰でもない私」にたどり着くでしょう。「誰でもない」とは「無名の」という意味にもとれますが、「世界で一人しかいない」という意味にもなります。私の体験は私以外の人には体験できないことなのです。
(『あなた自身のストーリーを書く』第1章 心の世界を楽しむ 9~10ページ)
もう一つの「リーディング・ライティング(読んで癒される)」は、スピリチュアル系の分野でよく使われることばだが、ここではさきに【「ブック」を「読む(read)」行為は読み手の〈からだ/歴史的身体〉のなかに新しい文章を「書く(write)行為である】と述べたように、「ブック」に記された文字を単に眼で追うことではなく、それは「歴史的身体」という「からだ(自分)」のフィルター(成育環境・経験・記憶)を通して「読む(reading)行為であり、それはまた、〈からだ/歴史的身体〉に上書き(overwrite)する行為でもある。
ある意味で、「ヒーリング・リーディング」と「ヒーリング・ライティング」とは、表裏一体のもの、〈からだ/歴史的身体〉という同じコインの裏と表のようなものだ。
「ブック(書籍)&マガジン(雑誌)」は、書き手(書籍は作家/雑誌は取材記者)の「つたえたい」思いを、読み手(読み聞かせの場合は聞き手)に「つたわる」ように届ける最強の「メディア」である。メディア(media)はラテン語のmedium(中間の、媒介者)に由来し、現在では「情報媒体」を意味する言葉として使われている。
かつて私が、武蔵野大学で「コミュニケーション論」を講じたときに、「メディアはお母さん(※お父さんでもよい)が作る昼食弁当である」と話したことがある。たとえば、母親が子どものために作った「昼食弁当」があったとする。子どもが昼休みにその弁当を食べるとき、弁当箱に入っているご飯やおかずは、科学的に言えばもちろん「物体」であるが、その子にとっては単なる「物体」ではない。この子に食べさせようと前の晩から献立を考え、早起きして作った母親の愛情を感謝していただく、つまり(弁当箱の)ご飯やおかずを通して、慈愛のこころ(メッセージ)をいただくことにほかならない。
マーシャル・マクルーハンは「メディアはメッセージそのものだ」と喝破しているが、この昼食弁当の譬えでいえば、「(ご飯とおかずの入った)弁当箱」がメディア、「おいしく食べてほしい」と願う母親の気持ちがメッセージであると考えられないだろうか。
母親とその子どもは日々の「昼食弁当」を介して、「召し上がれ」と「いただきます」というメッセージを共有し、親子ならではの濃密なコミュニケーションを図ることができる。
「メディアの両側には人がいる」(中島誠一著『現代メディア論』)という言葉は、近年のマスコミ(マス・メディア)編集者が、「弁当箱(メディア:容器)」に入れる「ご飯やおかず(コンテンツ:中身)」の豪華さや奇抜さをてらうあまり、本来の「伝えるべきメッセージ」を入れ忘れていないかと、猛省を促す「メッセージ」となっている。
作家の五木寛之さんは、徹底した「他力本願」を説いた仏教指導者、法然(浄土宗開祖)・親鸞(浄土真宗開祖)・蓮如(本願寺八世宗主)について、それぞれの布教スタイルの違いを次のように書いている。
法然は「むずかしいことをやさしく(難しいことを易しく)」、親鸞は「やさしいことをふかく(易しいことを深く)」、蓮如は「ふかいことをひろく(深いことを広く)」伝えた。
マス・メディアがいま、本当に「伝えるべきメッセージ」の源泉が、ここにある。ちなみに、エンタメ系のホリプロ本社受付脇のロビーには、次の言葉が掲げられている。
「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく」
これからも、「やさしく、ふかく、ひろく、おもしろく」、そして「心あたたかなメッセージ」を心がけながら、本コラムを「つたえる/つたわるメディア」にしていきたい。
【プロフィール】
原山 建郎(はらやま たつろう)
出版ジャーナリスト・武蔵野大学仏教文化研究所研究員・日本東方医学会学術委員
1946年長野県生まれ。1968年早稲田大学第一商学部卒業後、㈱主婦の友社入社。『主婦の友』、『アイ』、『わたしの健康』等の雑誌記者としてキャリアを積み、1984~1990年まで『わたしの健康』(現在は『健康』)編集長。1996~1999年まで取締役(編集・制作担当)。2003年よりフリー・ジャーナリストとして、本格的な執筆・講演および出版プロデュース活動に入る。
2016年3月まで、武蔵野大学文学部非常勤講師、文教大学情報学部非常勤講師。専門分野はコミュニケーション論、和語でとらえる仏教的身体論など。
おもな著書に『からだのメッセージを聴く』(集英社文庫・2001年)、『「米百俵」の精神(こころ)』(主婦の友社・2001年)、『身心やわらか健康法』(光文社カッパブックス・2002年)、『最新・最強のサプリメント大事典』(昭文社・2004年)などがある。
-
連載「つたえること・つたわる...
〈泣いて〉生まれて〈笑って〉死ぬー〈いのち〉の臨界点をさぐる
連載 2024-06-27
-
連載「つたえること・つたわる...
そのときは「家」でー〈なかよし〉時間、〈自然死〉ハイライト。
連載 2024-06-13
-
連載「つたえること・つたわる...
「生」から「死」へー自然体で旅立つ〈いのち〉の「間(あはひ)
連載 2024-06-06
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまりの日本語――きこゆ・うたふ・かたる・つたふ「オノマト
連載 2024-03-26
-
連載「つたえること・つたわる...
ゆかいな日本語――逆さことば、しりとり、あたまとりをたのしむ
連載 2024-02-27
-
連載「つたえること・つたわる...
気になる日本語――同音異義語、異字同訓をダジャレ、謎かけであ
連載 2024-02-13
-
連載「つたえること・つたわる...
地名――大地に記された〈あしあと〉、語り継がれる〈ものがたり
連載 2024-01-23
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまり:由来→これまで:変遷→いま:現在→これから:将来。
連載 2024-01-09
-
連載「つたえること・つたわる...
エンゼルス(天使たち)から、ドジャース(ブルックリンの子ら)
連載 2023-12-26