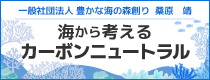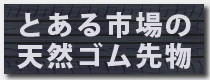連載「つたえること・つたわるもの」延長戦2
そのときは「家」でー〈なかよし〉時間、〈自然死〉ハイライト。
連載 2024-06-13
出版ジャーナリスト 原山建郎
野の花診療所院長・徳永進さんの最新刊、『いのちのそばで』(朝日新聞出版、2024年2月28日第一刷)を手にとると、副題に「野の花診療所からの最終便」と書かれていた。
「最終便」とは、ただごとではない。目次で拾った「白内障 手術秘話」、「右鼠蹊部剃毛指示」を読むと、それは患者のことではなく、徳永医師自身のことであった。
えいやっと「あとがき」を読む。京都大学医学部卒業後、26歳で医師になり、64歳で新聞の連載コラムを書き始め、いま75歳を迎えた徳永さん50年の〈自分史〉ハイライト。
医学部を卒業したのが1974年3月。医師免許を与えられたのがその年の5月30日。ぼくは26歳。初めて主治医になるのがその年の6月上旬。初めて患者さんの死に立ち会うのが8月ごろ。死を告げると、後ろの方から娘さんが急にベッドに走り寄り、もう亡くなった60歳の患者さんにしがみついて「お父ちゃん、死んだらいけん、死んだらいけん」と叫んだ。臨床って、すごい場所だ、と初めての症例で教えられた。教科書には書かれていない、書きようがない出来事がそこでは日々起こっている。書きとめられていない言葉も日々発せられていると知った。
生まれ故郷は鳥取。故郷でも多くの人が病み、この世を去っていかれるのだろうと思った。ぼくは30歳、若い医師。心の中に「故郷という方法」という言葉が生まれた。(中略)
連載が始まったのは2012年4月。ぼくは64歳。もう11年半も前のことになる。臨床の日常を綴っていった。臨床というフィールドでいろんな患者さんや家族に出会い、そこで起こった出来事や発せられた言葉、発せられる前の言葉を、ただ臨床報告として綴った。正当化をなるべく避けて、ただ事実を綴った。今回の原稿もそんな中で生まれていった。
新聞に連載(朝日新聞中国地方4県版)した最初のまとめは『野の花あったか話』(岩波書店)、次が『まあるい死』(朝日新聞出版)になった。今回は2019年から2023年の連載が一冊にまとめられた。臨床医として働き始めて50年。初めての死の病室からこんなにも経った、と自分でもあきれる。ぼくは臨床医でいることしかできなかった。(中略)
臨床は今までがそうであったように、これからも休むことなく大波の日や小波の日を繰り返していく。でも次の一冊を作れるだけの臨床力はもうないだろう、と冷静に考える。サブタイトルに「野の花診療所からの最終便」とさせてもらった。ぼくは75歳。
(『いのちのそばで』「あとがき」260~263ページ)
連載コラム「つたえること・つたわるもの」№123(2021年10月)で、評論家の米沢慧さんが、在宅ホスピス医、内藤いづみさんを「いのちの番人」と呼んだように、今回、「野の花診療所からの最終便」を著した徳永さんを、〈いのち〉の守り人と呼ぶことにしたい。
〈いのち〉という「やまとことば(上古代の口承言語)」は、いくつかある語源解釈のひとつに、【「い」は生命力を生み出す「いき(息・息吹く)」+「の(AとBを結びつける格助詞)+「ち」はスピリチュアルな力を意味する「ち(霊)」】がある。
この〈いのち〉は、「生」と「死」をひとつに貫いて生きる〈いのち〉。あえて誤解を恐れずにいえば、死んだのちも生きつづける「生死一如」の〈いのち〉のことである。
たとえば、在宅ホスピス医でもある徳永さんは、在宅の患者さんを看取り、死亡診断書という名の「人生の卒業証書」を家族に渡したあとも、近くを往診で通るときにはその家に立ち寄るという。愛する家族のこころに、永遠に生きつづける〈いのち〉の守り人である。
徳永さんには、いくつの目があるのだろう。高齢のがん末期の男性を、在宅で世話をする元看護師、82歳の妻と、「将来、看護師になりたい」という、小学六年生の孫娘の奮闘ぶりに、「二人の看護師」というタイトルをつけたコラムが、野の花診療所HP(2015年7月29日)に載っている。
二人の看護師
88才のがん末期の男性が、在宅療養をと、紹介になった。82才の奥さんと二人暮らし。余命は一ヵ月と説明受けた。4年前の手術は成功したのに、と悲しみと怒りが入り混じる。痛み、頻尿、咳に息切れ、食欲不振、たくさんの苦痛がある。確かに長い命は難しい。あれやこれやの工夫がいる。看病も大変な時を迎える。
奥さんに今後のことなど説明して帰ろうとすると、「私、昔、看護婦でした」と。古い県立病院の看護学校の卒業生とのこと。「そうですか、そりゃ心強い。看護主任に任命す」と玄関で言うと、「役にゃ立たへん」と嗄れ声の患者さん。「ほんとほんと」と奥さん。何か温かい空気が流れた。
だったら、と思いついた。薬が効かなくなる時がある。薬が飲めなくなることもある。安定剤の注射が苦しさをやわらげることがあって、いつもはできないが、元看護師の奥さんになら頼める、と思った。「いいですよ」と主任さん、やる気になった。夜、電話で指示。預けた注射、よく効いた。
二人暮らしのこの家に、夕方、小学6年生の女の子がやってきた。近所に住む孫娘。小さい時から夕食はここで食べた。「将来、看護師になりたい」と言って、おじいちゃんの世話をよくした。訪問看護師が手作りネームプレートを胸につけてあげると、小さな無資格看護師が生まれた。部屋が一層温かくなった。
病状は進行。主任の顔にも疲労の色。いよいよ、という日、無資格看護師も当直することになった。主任の顔が急にほっと明るくなった。「二人でみてあげようね」。翌朝の四時半、患者さんは元と未の二人の看護師に看取られた。
(野の花診療所HPコラム『野の花あったか話』第64回「二人の看護師」)
1986年に在宅看護研究センターを立ち上げた、開業ナースの草分けである村松静子(むらまつせいこ)さんはいま、たくさんの〈いのち〉のメッセンジャーナースを育てている。
村松さんが2002年に上梓した『そのときは家で――開業ナースがゆく』(日本看護協会出版会)に、〈いのち〉のメッセンジャーナースとしてのエピソードが書かれている。
村松さんが在宅看護にかかわった中に、38歳で亡くなった女性がいた。彼女は30代初めに卵巣がんと診断され、その後も転移による入退院を繰り返しながら働きつづけた気丈なキャリアウーマンだった。入院中、個室に移った彼女は、日に日に病気のことしか考えられなくなったある日、両親との面会時に、「どうしても家に帰りたい」と訴えたという。
両親から相談された訪問看護師の村松さんたちは、まず、医療関係者、家族との面談で、在宅での看取りの可能性などを話し合った。そして、患者本人との面談を行った。
面談のあと、本人と初めてお会いしました。「家に帰れるようにします。どうぞ安心してください」そう伝えると、こわばって他者を寄せつけない雰囲気だった彼女が、にこっと笑顔を見せてくれました。
自宅に戻った彼女は自分の部屋で過ごすことに強い思いを抱いており、外に出ることはありませんでした。医療的な処置は姉が私たちナースや本人から教わりながら行うようになっていきました。家族は、それぞれの役割を分担するなかで、彼女が近いうちに死ぬのだという事実を受け入れ、覚悟していったのです。
亡くなる前日、彼女は「家のお風呂に入りたい。チューブは全部とって、元気なころのように、普通にお風呂に入りたいの」と希望しました。担当ナースから電話で相談を受けた私は、彼女の希望に最大限に近い形で沿うため、医師と連絡をとり、許可を得ました。中心静脈栄養接続のためのポートだけはそのままでビニールのシートで覆い、その他のチューブははずした状態でお風呂に入った彼女は、周囲が驚くほど伸びやかでリラックスした表情になりました。
翌日、彼女は逝きました。両親が用意した晴れ着をきて、とても和らいだ顔をしていました。ふっと起き上がりそうな若く美しいいその姿を私は忘れられません。
(『そのときは家で』「家で死にたい」という希望を叶えられない理由 21~22ページ)
「いのちの番人」と呼ばれた在宅ホスピス医、内藤いづみさんの著書『最高に幸せな生き方 死の迎え方』(講談社、2003年)に、「静かで平和な旅立ち」と題する一文がある。
昏睡状態であると説明した日から、奥さんは覚悟を決めたようだった。
川井さんはこんこんと眠り、時折、声をかけると起きて、食事をとったりしていた。おかゆを茶碗に半分とか、ゼリーとか。
「眠っていると楽です。背中も楽ですから、心配しないでください」
と言ったり、赤い腰ベルトの看護師さんが好きで、
「一〇メートル先でも足音でわかるよ」
と言ったり、
「眠ってばかりで悪いですね」
と言ったりしている。川井さんは最期まで人を気づかい続けていた。
三日後に河合さんは危篤状態になった。奥さんと二人の娘さんとそのご主人、お孫さんたちも、みんな川井さんの枕元で見守り続けた。川井さんがとても可愛がっていたお孫さんたちが、手を握って「おじいちゃん、おじいちゃん」と呼びかけると、川井さんは手を握り返して応えた。
「ご家族の方が主役で私たちは脇役ですから」
看護師さんは部屋の隅に座って、夜中もつき添った。
翌朝、川井さんは川井さんの人生にふさわしく、静かに平和に息を引き取った。最期の深くて長い呼吸がしばらく続き、私がホスピスの勉強をしたイギリスだったら、こんなとき牧師さんはお祈りをして、讃美歌が歌われるだろうと思った。お孫さんに「おじいさんの好きな歌は?」とたずねると、「加藤登紀子」と教えてくれた。私は心の中で、「ハマナスの咲くころ~」と「知床旅情」を歌った。誰にも聞こえないだろうが、きっと川井さんにはその声が届いていると思いながら。
愛するご家族との別れを名残惜しむように、川井さんがゆっくりと息を引き取る瞬間、娘さんには「ありがとう」とお父さんが言ったように見えたという。
ずっと関わってきた看護師さんたちがからだを清め、奥さんが用意したスーツとネクタイに着替えた川井さんは、とてもハンサムでやさしい顔をしていた。
その日、藤の花は五分咲き。満開になったのは、ちょうど初七日の法要のころだったそうだ。
(『最高に幸せな生き方 死の迎え方』「最期まで慣れた家で過ごしたい」45~46ページ)
前回のコラム№182「生」から「死」へ――自然体で旅立つ〈いのち〉の「間(あはひ)」。で紹介した上田医院院長・上田聡さんは、〈いのち〉のグッド・ドクターである。
肺がん末期、病院で抗がん剤治療を受けていた27歳の青年「高志」が「どうしても退院したい」と言い出した。相談を受けた上田さんは、二つ返事で訪問診療を引き受けた。
高志の診療情報からも、相当状態が悪いことはわかった。病院の先生から直接電話をいただき、「いつでも受け入れます」と言われていた。介護タクシーで帰ってきた高志を、僕と看護師の松さんと高志の母と姉の四人で迎えた。日曜日の昼に、姉から電話がかかってきた。「高志が先生に会いたいと言っている」と。ちょうど昼の外食していた僕はその帰りに高志の待つマンションに直行した。(中略)
高志はあまり饒舌ではなかった。僕が話しかけても会話はあまり続かない。だいたい姉が「高志は実は○○なんだよね」とか、「高志はこうだよね」と代弁して会話は終わる。高志は「うん」とうなずくのが常だった。
その日は、「怖くて眠れないのだ」と言った。「大丈夫だよタカ、私たちがついているじゃない」と姉は言う。高志は姉と視線を合わせない。これから一人で旅路に就く彼に、僕たちは何と声をかければいいのだろうか。僕には、かける言葉が見当たらなかった。時計の音がチクタクチクタク。高志の手が僕の近くに伸びてきた感じがしたので、僕は彼の手をつかんだ。まだしばらく沈黙が続いた。
母親が「タカ、いい加減にしなさい。先生は忙しいんだから」というと、「そうよ、タカ」と姉も言う。しかし、彼の手はゆるまない。片手で紅茶とケーキを食べながら、なんとか場の空気を和ませようと気の抜けた感じで「まあまあ、大丈夫ですよ」と僕。こんなやりとりが何度か続いた。そしてついに出た一言にグッときた。
「怖いんだよ。最後ぐらい、僕の好きにさせてよ」
母も姉もその後は沈黙。ぼくはひたすら彼の手を握っていた。彼の手の握る力は周期的に強くなったり弱くなったりしていた。時計の針が夜の九時を指した頃、高志の手は僕の手から離れた。高志は「もう大丈夫だよ」と言った。僕はゆっくり立ち上がり玄関に向かった。玄関先で母と姉から「これからは私たち家族だけで看ていきたいと思います。先生、本当にありがとうございます。また何かあったら、こちらから電話します」と言われた。
それから三日後、電話が鳴った。「今、高志が息を引き取りました」とのことだった。
看護師の松さんと母と姉とで、高志の死後処置が始まった。愛用のジーンズにTシャツを着せた。高志のジーンズはダボダボだった。
退院後の濃密な三週間だった。後日クリニックに挨拶に来てくれた母と姉からは「いい時間が過ごせてよかった」と、悲しみの中にもやりきったという感じが漂っていた。僕も病気に負けたという敗北感はなかった。やりきった感じだった。彼の人生は確かに短かったけれども僕は天寿をやはり全うしたのだと感じた。「老衰」というと「老ではないぞ」と彼にこっぴどく怒られるだろう。若くして天寿を全うしたという意味での適切な言葉がまだ見つからない。
(『在宅医療のリアル 改訂版』「第6章 最期の質」138~141ページ)
今回のコラムで紹介したエッセイはどれも、心の奥底にズンと響く〈自然死〉ハイライトだったが、最後に、野の花診療所HPにあった、〈いのち〉の守り人、徳永さんの連載コラム『野の花の人々』から、第65回(最終回)「なかよし時間」を紹介したい。
このエピソードは、野の花診療所の二階に19床あるホスピス病棟で、穏やかな〈自然死〉(ナチュラル・ダイイング)を迎えた元小児科医、向田先生の「旅立ちの光景」である。
ここはもう「ホスピス病棟」の建物ではあるが、向田先生を愛する家族、心を込めてケアする医療者という「形のない家族」にとっては、もう一つの「わが家」であった。
「家(いえ)」を旧仮名遣いで「いへ」と訓読する「やまとことば(上古代の口承言語)」の語源を辿ると、【「い」は生命力を生み出す「いき(息・息吹く)」+「へ」は生きるエネルギーが集まる「あたり(辺)」を意味する「へ(辺)」】説が有力で、「家(いへ)」は「廬(いほ)」と同根の語である。あるべき「家(いへ)」のかたちとは、家族ひとり一人がお互いに思いやりをもって「なかよし時間」を共有する「〈いのち〉の居場所」なのである。
夜の七時「1号室へ急いでください」と夜勤のナース。診察室を飛び出て二階に走った。無言の八十四歳の元小児科医の向田先生。脳梗塞で長年寝たきり、手足に強い拘縮がある、何度も死線をさまよわれた。今回はいつもと違う緊迫感が漂う。顔色悪く血圧六〇。
先生はいろんな菌の敗血症を繰り返した。かかっては治り、治ってはかかり。慢性敗血症と言う病名を先生から学んだ。長男は神戸、長女は鳥取。病状悪化のたびにぼくは召集令状乱発。全員そろうと病状は落ち着く。先生もぼくもおおかみ少年。入院してもうすぐで一年だ。輸血が始まる。
詰め所にいると、1号室からナースが呼ぶ声。走る。下顎呼吸だ。脈は触れない。「しまった」と思った。先生の最期の時、奥さんに手を握っていてほしかった。夕支度で留守。「頑張って、向田先生」とナース。「奥さん、呼んで」「先ほど連絡しました」。呼吸は止まった。瞳孔は散大。残念、間に合わない。「ボスミン(強心剤)一アンプルiv(静注)!」「はい」とナースは詰め所に走り、飛んで帰ってきた。「ボスミン入れます」。呼吸は止まったまま、脈も触れぬまま。
「桜も蛍も花火も見、神社の祭りも、もちつきも見、正月も豆まきもしました。もうすぐ先生の誕生日ですよ、頑張ってー」とナース、ギュッと先生の手を握る。病室に弦楽器による静かな宗教曲が流れていた。しばらくたって、先生の顎が動いた。小さい下顎呼吸が生まれた。首の脈が触れた。奇跡だ。廊下に足音がした。ドアが開いた。奥さんと長女。「ダメでしたか?」、「いいえ」。
一度死が来たが、励ましと曲と一本の注射で、今、先生復活、と説明した。「ああよかった」奥さん、顔を崩す。あとを三人に任せた。ぼくは他の病室を回診した。遠く1号室あたりで、笑い声が廊下に漏れる。
「母が今、父の頬に、何度もキスしたんですよ」「何年もこんなことしたことないのに、私。でもうれしい」「あっ、父さん、目開いたよ。母さんのキス、薬より効く」。1号室に死の間際のなかよし時間が流れた。
二時間後、先生、二回目の、ほんとの他界。零時を回って長男到着。「父も母もいい顔で、感謝です」と穏やかな口調だった。夜半すぎ、先生と長男が乗った車を、ぼくと二人のナースで見送った。向田先生の長い闘病の日々を思うと、頭が下がった。「ご苦労様でした」。診療所の玄関でさよならをした。
読者の皆さんとも今回でさよなら、お元気で。
(野の花診療所HPコラム『野の花の人々』最終回「なかよし時間」)
家(いへ)という名の〈いのち〉の居場所で、たくさんの〈自然死〉ハイライトを見守る――〈いのち〉の守り人、〈いのち〉のメッセンジャーナース、〈いのち〉の番人、〈いのち〉のグッド・ドクターの皆さんに、心からの〈ありがとう〉を捧げたい。
【プロフィール】
原山 建郎(はらやま たつろう)
出版ジャーナリスト・武蔵野大学仏教文化研究所研究員・日本東方医学会学術委員
1946年長野県生まれ。1968年早稲田大学第一商学部卒業後、㈱主婦の友社入社。『主婦の友』、『アイ』、『わたしの健康』等の雑誌記者としてキャリアを積み、1984~1990年まで『わたしの健康』(現在は『健康』)編集長。1996~1999年まで取締役(編集・制作担当)。2003年よりフリー・ジャーナリストとして、本格的な執筆・講演および出版プロデュース活動に入る。
2016年3月まで、武蔵野大学文学部非常勤講師、文教大学情報学部非常勤講師。専門分野はコミュニケーション論、和語でとらえる仏教的身体論など。
おもな著書に『からだのメッセージを聴く』(集英社文庫・2001年)、『「米百俵」の精神(こころ)』(主婦の友社・2001年)、『身心やわらか健康法』(光文社カッパブックス・2002年)、『最新・最強のサプリメント大事典』(昭文社・2004年)などがある。
-
連載「つたえること・つたわる...
〈泣いて〉生まれて〈笑って〉死ぬー〈いのち〉の臨界点をさぐる
連載 2024-06-27
-
連載「つたえること・つたわる...
書き手も読み手も癒すメディアーブック(書籍/雑誌)セラピー。
連載 2024-06-20
-
連載「つたえること・つたわる...
「生」から「死」へー自然体で旅立つ〈いのち〉の「間(あはひ)
連載 2024-06-06
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまりの日本語――きこゆ・うたふ・かたる・つたふ「オノマト
連載 2024-03-26
-
連載「つたえること・つたわる...
ゆかいな日本語――逆さことば、しりとり、あたまとりをたのしむ
連載 2024-02-27
-
連載「つたえること・つたわる...
気になる日本語――同音異義語、異字同訓をダジャレ、謎かけであ
連載 2024-02-13
-
連載「つたえること・つたわる...
地名――大地に記された〈あしあと〉、語り継がれる〈ものがたり
連載 2024-01-23
-
連載「つたえること・つたわる...
はじまり:由来→これまで:変遷→いま:現在→これから:将来。
連載 2024-01-09
-
連載「つたえること・つたわる...
エンゼルス(天使たち)から、ドジャース(ブルックリンの子ら)
連載 2023-12-26